物部氏の神社 名古屋市味鋺神社

皆さん、お疲れです。
アヒルノヒカリでございます。
この頃ちょくちょく名前が出てくる味鋺神社、本日はこの神社を参拝します。
味鋺神社
味鋺神社は物部氏が建てた式内社、という事は分かっています。
式内社という事は周辺は古くからある町という事ですから、古くからありそうな道を選んでみました。

堤防から降りてくるこの斜めの道、いかにもな感じです。

少しだけクネクネしていますね。


道の交わり方がカオス、きっと古くからある道なのでしょう。

この細い道の奥に神社が見えます。


・・・・が、この斜めの道は神社の正面には出ません。

味鋺神社の正面に到着です。



因みに「あじま」と読みます。


鳥居を潜ったすぐにある百度石、その向こうにベンチが見えますね。
神社の境内にベンチ・・・・珍しい。


そして立派なクスノキ。

新しい雰囲気の手水舎、残念ながら水はありません。

清正橋、ここから南西100mの場所に架かっていたこの清正橋を昭和53年に移築したそうです。
名古屋城築城の折に加藤清正の命で架けられたとの事で、名古屋から中山道まで続く稲置街道に架かっていたそうです。

そういえば数年前に一度稲置街道の道標に遭遇しましたね。

此方は庚申塔、中国の道教由来の庚申信仰に基づいて全国各地つくられたとの事です。
初めて知りました、神社にあるこの形の物は全て庚申塔なのでしょうか?
此方の庚申塔は江戸末期から明治初期に作られた物だそうですよ。

ロータリー?
何だかモダンな雰囲気ですね。
・・・・。
・・・・正直にお話し致します。
実を言いますとこの神社、随分前に一度来ています。
その時は物部氏も東西の八龍神社との関係も知りませんでした。
ただ地域名が名前になっている神社は古い神社だろうと興味を持ちました。
ですが来てみると物凄く工事中という風景・・・・参拝は出来ましたがとてもここでご紹介できる状態ではありませんでした。
ですから深く調べる事を控え、いつかまた来ようと・・・・。
ここ数ヶ月の間の他の神社を参拝した繋がりでその”いつか”がきた訳です。
新しい手水社やベンチ、このロータリーみたいな道はその時の工事で造られたのでしょう。



木を囲うおみくじ。

此方にも立派な木があります。
このチラッと写るネイビーの建物はトイレ・・・・此方も工事で建てたのでしょう。



美しい屋根。

そして美しい龍の彫り物。

本殿左にズラッと並ぶ境内末社、見応えがありますね。

右には味鋺の流鏑馬、神馬の像ではなく流鏑馬の像とは珍しいです。

そして此方が本殿。

早く戦争が終わりますように・・・・。
ありがとうございました。
帰宅後調べました。
創建年は不明ですが式内社ですので平安時代以前、祭神は物部氏の祖である宇麻志麻治命と息子の味饒田命です。
かつてこの周辺、庄内川の北側には100を越える古墳があったそうです。
そして庄内川南側には多くの六所神社、祭神は伊邪那岐命と伊邪那美命系統の神々という事なので・・・・やはり庄内川が境界線だったのでしょう。
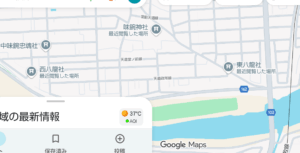
味鋺神社と西八龍神社、東八龍神社の間に古くからある大きな道がありそうだなとウロウロしてみましたが・・・・。
Googleマップを拡大すると「天道政所線」や「上街道」など古くからありそうな道の名前を確認出来ます。
政所線だなんて如何にも中心地っぽい名前です。
ですがウロウロしても碁盤とまではいきませんが整った道、規則正しく並ぶモダンな住宅、逆に昔からありそうな大きい日本家屋と広い庭園・・・・こういう住宅はありません。

天道政所線と味鋺神社へ続く道の交差点、この一角だけですが田んぼがあります。
昔この辺りは湿地帯が広がっていて水田に適していたそうです。
もしかしたら味鋺神社の南側は水田地帯だったのかもしれませんね。
そしてその水田地帯を庄内川の水害から守るべく東西に八龍神社を建てた・・・・現代の地図を見て想像してもあまり意味は無いでしょうが、そんな気がします。
庄内川と東西の八龍神社が物部氏の勢力圏、川の南側とは別系統の神域の境界線であるならば・・・・。
先日ご紹介した物部神社、物部白龍神社は元々別の神を祀った神社だったという説はとても頷けます。
調べて知った諸説を現地をウロウロする事で実感出来る、ど素人ですがそういう事もあるかも知れませんね。
皆さんの町にはどんな神社がありますか?